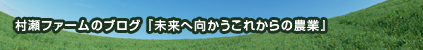行者ニンニクは種を播種してから7〜8年栽培して収穫期を迎える。気の遠くなるような栽培期間を持つことから、途中で挫折したり、栽培意欲が減退する栽培農家が多い。
1個の種子から大きな株となって写真のように親指より太い葉茎となる。例年収穫しているものは太くても親指程度あったが、今年は異常に太いものがぞろぞろと収穫されている。
堀取られた行者ニンニクは株分けして、古い根をハサミ等で取り除き専用のコンテナに収容する。土とバーク堆肥を混和したものをコンテナの高さと同じくらい上にまぶす。この土の量によって軟白の長さが決まる。好みがあるが、食する時は軟白の部分が甘みがあり、滋養強壮の成分が豊富で美味しい。
行者ニンニクは強い生命力を持ち、凍結しても新しい根が発根して、春の季節の到来とともに冬眠から目覚めるのである。よって滋養強壮としての成分が作物自体に備わっている。
例年、株分け時に年数不足の細い行者ニンニクは再び圃場に戻されるが、今年はほとんど見かけられない。暑さを嫌う山菜なので、朝晩の寒さが厳しかった天候が好影響しているようである。
現在はほとんど北海道で消費され、『幻の山菜』としての位置づけになっていることを打破したいが・・・。7〜8年かかる栽培期間がネックとなってゆっくりしか栽培面積を増加させることができない。これでは商品の供給(年300〜400キロ出荷)もままならぬ現状である。単年度の換算で10a当たり30〜40万円程度の収入があり、仕事のない冬期間に作業が確保できることが魅力でもある。何とか頑張って、栽培意欲をかきたて拡大してゆきたいと考えている。