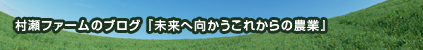10月25日、26日のマイナス2〜3度の気温ですっかり色付いた長芋のツル。ツル落とし、約6000本の支柱ポール抜きをして準備を終えた。ポール抜きの作業は軽量ポールでも本数が多いので大変な作業になっていた。そこで希望の多かった、青森県のT技研の支柱ポール抜き取り機を買うことにした。
今年度はT技研の収穫時に使用する台車「台助くん」、補助事業(導入価格の3分の2)で帯広市T社の4畦ホイールトレンチャー、マルチ回収機などを導入した。毎年、長芋関連の機械を買っていますが作業効率や重労働からの脱却、軽減のために導入している。「台助くん」は使用してみて評判は上々、凹凸のある地面を歩かないので作業が格段に楽になった。マルチ回収機は一度に5本ほど(従来は1本)回収可能で作業速度が一気に上昇した。働く環境を整える投資は絶対に必要で無駄な投資ではない。節約するところは他にたくさん存在する。
作柄は昨年よりも歩留まりが良好で、規格外率は低い数値で推移している。奇形はほとんど見られない。長芋栽培が初めての圃場で、まだ一巡していないのが最大の要因だと思う。今のところ自家製長芋播種機の成果は「優」の状態である。